アイゾメヤドクガエルの飼育・繁殖情報

アイゾメヤドクガエル
(熱帯域のカエル)
難しい
うつ病になりやすい
※上記はGoogleMap上での代表地域を示したものです。厳密な生息範囲ではありませんので、参考情報までに。
主な特徴

「アイゾメヤドクガエル(Dendrobates tinctorius)」は、美しいカラーパターンの大型ヤドクガエル。
体色は青色・黄色・白色など非常に多彩でありますが、本種は地域によって大きくカラーパターンが変わるのが特徴です。モルフが異なれば別のカエルのようなカラーとなり、古くから今なお世界中の愛好家を飽きさせません。
昼行性で小さな虫を何度も摂食するスタイルの生活を行うため、鑑賞性がとても高いのも大きな魅力と言えるでしょう。一部モルフを除き、基本的にはオープンスペースでエサを探し回る様子を観察できます。
なお強烈な毒を持っていると思われがちですが、毒は現地の虫を食べることで生成されます。本種は野生採取個体が販売されることはまずありませんので(ほぼ)無毒です。(日本のアマガエル程度の弱い毒性)




モルフ(バリエーション)
アズレウス

全身が青色で、黒スポットが入るのが特徴の中型モルフです。
他モルフと比べると頭一つ抜けて「うつ病」になりにくく、アイゾメヤドクガエルの中では最も飼育が容易です。隠れることもなく前に出てきてくれますので、行動の面からも非常に鑑賞性は高いでしょう。
無効の旧名:コバルトヤドクガエル
本モルフを「コバルトヤドクガエル」と呼ぶのは不適切です。
2006年以前では「Dendrobates azureus」として別種で分類されており、その和名として「コバルトヤドクガエル」が与えられました。しかし2006年の研究で「Dendrobates tinctorius(アイゾメヤドクガエル)」の地域変異であることが分かり、azureus種は無効になっています。
加えてアイゾメヤドクガエルには「コバルト」というモルフがおり、名称が重複することからも「コバルトヤドクガエル」と呼ぶことは避けて下さい。
ブラジル(ブラジル・コバルト)

アイゾメヤドクガエルでは最も代表的なカラーパターンを持つのが「ブラジル」です(中~大型モルフ)。
いわゆるコバルト系カラーと言われ、頭部から背面にかけて黄色のパターンがのり、腹部は青・白色のグラデーションが表れます。手足はアイゾメの名らしく紺色に染まるのも特徴でしょう。
別モルフの「コバルト」と見た目が多く重複する部分がありますが、コバルトは元の採取地がスリナム共和国であり、ブラジルはその名の通りブラジルであるため地域的には異なる個体群です。よって海外ではコバルトを「スリナム・コバルト」、ブラジルを「ブラジル・コバルト」という名称で扱われたりします。
トゥムクマケ

ブラジルのトゥムクマケ国立公園をルーツに持つ中型モルフ。全身がうっすら青みのかかった灰色で、吻部・肘・脚部(ヒザ~カカト)が黄色くなるのが特徴です。
オイヤポッキ

ブラジルとフランス領ギアナと国境沿いにあるオイヤポッキ川周辺をルーツに持つモルフ。黒をベースに白色模様が入る美しいモルフであり、メジャーなモルフの中では小型なのも特徴です。
流通量も多く比較的人気のあるモルフですが、神経質な性格で「うつ病」になりやすく、メジャーモルフの中では本モルフが飛び抜けて飼育が難しいので注意しましょう。
飼育ポイント
導入時にストレスでうつ病になりやすいため、初期は細心の注意を払います。
本種はヤドクガエルの代表種として知られますが、ヤドクガエルの中では難しいグループです。
うつ病を発症しやすい
本種がヤドクガエルの難関種である一番の理由は「うつ病」になることです。
隠れ家のなさ、ケージの狭さ、同居ガエルとのストレスなど様々な要因で「うつ病」が発症してしまいます。うつ病を発症させてしまうと復帰はかなり困難なため、導入時にうつ病を発症させずに環境に慣らさせるかが最重要ポイント。
特に販売店で草・隠れ家がある「テラリウム」に慣れた個体の場合、購入後にプラケース・簡素なレイアウトへ移すような「良い環境からそれより悪い環境へと変化」させると、落差によるストレスを受けやすいので注意が必要です。

特にヤング個体はストレス耐性がないため、難易度が跳ね上がります。セミアダルトサイズであれば大きく飼育難易度は下がるので、特に理由がなければセミアダルト以上の個体を入手するのが良いでしょう。
なお同種での単独飼育はもちろんのこと別モルフとの同居も基本的には厳禁です。
うつ病の症状
ストレスを受け「うつ病」状態になった状態では、食欲が徐々に減衰し痩せていきます。すぐ死ぬことはなく、1~数ヶ月かけて死に向かっていきますので、そのような死に方をした場合は「うつ病」を強く疑って下さい。
成熟したメスがいるなら1ペアまで
ベビー~セミアダルトサイズでは同じケージに何頭でも飼育が可能なのですが、成熟したメスはテリトリー意識が出て、他の個体を排除しようとするので注意して下さい。
特にオスのメイティングコールを聞くとスイッチが入り、メスがそのオスを独占しようと他の個体に乗っかる・押し倒すなどのイジワル行為を行い始めます。場合によっては取っ組み合いの喧嘩となる場合もあり、非常にテリトリー意識が強いです。

写真はアズレウスなので比較的大丈夫なモルフだが、モルフ・状態によっては非常に危険。
それによりうつ病になると復帰は困難ですので、メスがいるなら同居できるのは基本的にオス1匹までを基本として下さい。(もちろん大きなテラリウムなど、空間が広ければ複数匹も可能です)
大型ヤドクの割にエサ虫が小さめ
本種は大型のヤドクガエルではありますが、エサはコオロギであればピンヘッド~SSS(2令)ぐらいが限度と、かなり小さい虫でないと食べてくれません。
基本的にはアダルトであっても「トリニドショウジョウバエ」「ヨーロッパイエコオロギのピンヘッド」がメインになります。ヤングサイズや調子がイマイチの個体であれば「トビムシ」も使っていきましょう。

そのほか、基本的な飼育方法は以下をご参照下さい。
繁殖
容易です。環境が整っていれば自然と産む傾向があります。
本種の飼育下繁殖は十分可能であり、流通する個体も基本的には自家繁殖されたものです。
特に梅雨時期はヤドクガエルの繁殖スイッチが入りやすく、自然と産卵行動を行う傾向があります。
雌雄の見分け方
アダルトになると「前足の手先にあるパッド(吸盤)のサイズ」で区別可能です。


オスはパッドが大きく広がりますが、メスはさほど広がりません。
注意点としてパッドはアダルト直前にならないと大きくならないのと、個体差があり「パッドの小さいオス」と「パッドが大きいメス」がいる場合判別は難しくなります。その点は念頭に置いた上で判別に臨んで下さい。
なおオスが発するメイティングコールは小声で「ジゥ・・・ジゥ・・・」と非常に小さく、事前に鳴き声を知っている人ですら、個体に顔を近づけてなんとか認識できる程度です。
繁殖の流れ
小さな洞窟など「屋根のあるくぼみ」の中に産む傾向があり、そのような産卵場所を用意するといずれ卵が見つかります。


2週間ほどでオタマジャクシは孵化し、孵化したオタマジャクシはオス親の背中に乗り込みます。
背負った親は水場を探してオタマジャクシを運びますので、プリンカップなど小さな容器に水を貯めておけば、オタマジャクシの回収が可能です。

オタマジャクシは熱帯魚用フードなどを与え、およそ2~3ヶ月ほどで子ガエルとなります。

その他・補足情報
代表種だが初心者キラー。必ずセミアダルト以上で
代表種なので入門種でもあると誤解されがちですが、よく販売されているヤングサイズはストレスに弱く、お迎え時の飼育環境・エサやりなど何か1つを失敗すると取り返しがつかない難関種です。
馴染んだ個体は物怖じせず手にも寄ってくるので、人によっては「ストレスに強いし簡単なヤドクガエルだよ!」と認識される方もいますが、それはあくまでも環境に馴染めた大きな個体の場合。
よってアイゾメヤドクガエルは、ストレス耐性のついた「セミアダルト」~「アダルト」個体を購入することが成功のマスト条件です。(あと販売ケージが作り込まれておらず、簡素だとなお良しだがこれは探すのが難しい)

輸入はヤング個体が中心となりますが、ひとふた周り高くてもお店で長期飼育されたセミアダルト~アダルト個体を強く推奨。ヤングはストレス耐性も低くあっさりうつ病になりますので、ヤングとセミアダルトでは圧倒的に難易度が異なります。
もちろん中々入荷しないレアモルフの場合は、死ぬリスクを大きく抱えてヤングにチャレンジしないと売り切れてしまう場合もありますが、そうでもない限り「ヤングサイズ」は専門店にケアを任せてセミアダルトサイズで購入するのをオススメします。
.
おたま商会では自家繁殖のアイゾメヤドクガエルの各種モルフを販売しております。
簡素なレイアウトでセミアダルト以上に育てることにより、新しい環境でのうつ病発症率が他店と比べて比較的低くなるよう努めております。是非一度ご検討下さい。

(左アダルト・右セミアダルト)
ブログでのレビュー/批評も歓迎!
参考文献
- 2006. GRANT, TARAN, FROST, DARREL R., CALDWELL, JANALEE P., GAGLIARDO, RON, HADDAD, CÉLIO F.B., et al. "PHYLOGENETIC SYSTEMATICS OF DART-POISON FROGS AND THEIR RELATIVES (AMPHIBIA: ATHESPHATANURA: DENDROBATIDAE)"
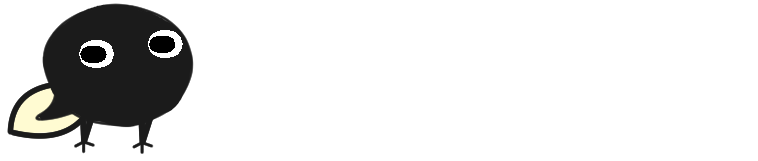











この記事へのコメント